「うちの学校には、いったいどのICT機器が一番合っているんだろう?」多くの教育関係者の方が、こんな悩みを抱えているのではないでしょうか。
文部科学省が推し進めるGIGAスクール構想で、全国の学校に1人1台端末が配備されました。
でも、Windows、Chrome OS、iPadOSと選択肢がたくさんあって、正直どれを選んだらいいのか迷ってしまいますよね。
この記事では、ICT教育の現場を知り尽くした視点から、皆さんの学校にぴったりのICT機器選びのコツをお伝えします。
きっと「これだ!」という答えが見つかるはずです。
GIGAスクール構想とは?ICT教育推進の背景と現状

GIGAスクール構想って聞くと、なんだか難しそうに感じませんか?
でも実は、その中身はとってもシンプル。一人ひとりの子どもに合わせた学びと、みんなで協力しながら学ぶ環境をつくることが目標なんです。
昔のように、先生が前で話して生徒がノートを取るだけの授業から、一人ひとりのペースに合わせた学習へ。
これこそがGIGAスクール構想の本当の狙いです。
実は、日本のICT教育はずっと世界から遅れをとっていました。
コロナ禍でその現実が浮き彫りになり、急ピッチで整備が進むことになったのです。OECD諸国と比べて最下位レベルだった日本にとって、まさに大きな転換点でした。
ICT教育とGIGAスクール構想
ICT教育のICTって、Information and Communication Technologyの略です。ITとちょっと違うのは、Communication(コミュニケーション)が入っているところ。つまり、一人でパソコンをいじるだけじゃなくて、友達と一緒に学んだり、先生とやりとりしたりすることも大切にしているんですね。
「1人1台端末」と「高速ネットワーク」という二つの柱で、教育現場をがらりと変えようというのがGIGAスクール構想です。コンピュータ室での週1回の授業から、毎日の学習で当たり前にICT機器を使う環境へ。鉛筆やノートと同じように、自然に使えるようになることを目指しています。
この変化によって、デジタル教科書がスムーズに使えるようになったり、生徒一人ひとりの学習状況がリアルタイムで分かるようになったり。先生たちの仕事も効率的になって、本当に大切な教育に時間をかけられるようになりました。

文部科学省によるICT環境整備の現状と課題
全国の小中学校で、1人1台端末の整備はほぼ完了しています。数字でいうと99.3%。すごい達成率ですよね!
でも、機器が揃ったからといって、すべてが順調というわけではありません。
一番大きな課題は、先生方がICTを上手に使いこなせるようになること。
「端末はあるけれど、授業でどう活用したらいいのか分からない」という声をよく耳にします。
高等学校の整備は小中学校よりも少し遅れていて、地域による差も目立ちます。
また、出席管理や成績処理といった校務をデジタル化することも、まだまだこれからの課題です。
運用面での悩みも出てきています。
「端末が故障したらどうしよう」「ソフトウェアの更新は誰がやるの?」「セキュリティは大丈夫?」など、導入後の管理について頭を悩ませている学校も多いようです。
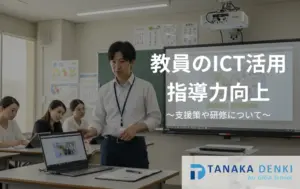
学校で導入すべきICT機器の選定ポイント

ICT機器を選ぶときに、カタログのスペック表ばかり見ていませんか?実は、それだけでは不十分なんです。
本当に大切なのは、導入してからの長い付き合いを考えること。
5年後、10年後も安心して使えるか、先生や生徒にとって使いやすいか、困った時にきちんとサポートしてもらえるか。
こうした点を総合的に判断することが成功のカギです。
特に重要なのは、「この機器を使って、子どもたちにどんな力をつけてもらいたいか」を明確にすること。
ゴールがはっきりしていれば、おのずと最適な選択肢が見えてきます。
導入目的と必要な機能の明確化
まず考えてほしいのは、「何のためにICT機器を導入するのか」ということです。
一人ひとりに合わせた学習を重視したいなら、学習履歴をしっかり記録できて、個人のペースに応じて教材を提供してくれる機能が必要でしょう。
みんなで協力して学ぶことを大切にしたいなら、画面を共有したり、同じ資料をみんなで編集したりできる機能が欠かせません。
先生方の仕事を楽にしたいという目的もありますよね。
出席をとったり、成績をつけたり、保護者と連絡をとったり。
こうした日常的な業務がデジタル化されれば、先生はもっと子どもたちと向き合う時間を作れます。
いろんな目的があると思いますが、まずは優先順位をつけてみてください。
そうすると、どんな機能が本当に必要なのかが見えてきます。

費用対効果と予算活用の視点
ICT機器にかかるお金は、最初に機器を買う費用だけではありません。
5年、10年使い続けることを考えると、メンテナンス費用、ソフトウェアのライセンス料、研修費用、サポートスタッフの人件費など、いろいろな費用が発生します。
この「トータルでいくらかかるか」を計算することを、TCO(Total Cost of Ownership:総所有コスト)と呼びます。目先の安さに惑わされず、長期的な視点で判断することが大切です。
GIGAスクール構想では国からの補助金が出ますが、その条件や範囲をきちんと理解しておくことも重要です。
補助対象の最低ラインを満たしつつ、将来的に機能を拡張できる余地があるかどうかも考慮しましょう。
複数年度にわたって計画的に予算を組むことで、一度に大きな負担をかけることなく、段階的に環境を整えていくことも可能です。

使いやすさ(操作性)とサポート体制
どんなに高性能でも、使いにくければ意味がありません。
特に、ICTに慣れていない先生方でも直感的に使えるかどうかは、ポイントとなっています。
起動に時間がかかったり、アプリの動作が重かったりすると、授業の流れが止まってしまいます。スムーズに動作することは、実は非常に重要なポイントなんです。
そして、困った時にすぐに助けてもらえるサポート体制があるかどうか。
故障した時の対応、操作で分からないことがあった時の相談窓口、定期的な研修プログラムなど、包括的なサポートがあると安心です。
ICT支援員との連携がスムーズにいくかどうかも、日々の運用では大きな違いになります。

学習者用コンピュータの比較と最低スペック基準
さて、いよいよ具体的な機器選びです。
現在、学校で主に使われているのはWindows、Chrome OS(Chromebook)、iPadOSの3つ。
それぞれに特徴があるので、詳しく見ていきましょう。
| OS種類 | 特徴 | メリット | デメリット | 最低スペック基準(抜粋) |
| Microsoft Windows | みんなが慣れ親しんでいて、いろんな機器とつながりやすい | プログラミングや動画編集が得意で、将来役立つスキルが身につく | 機種によっては電池の消耗が激しい。価格も幅広い | OS: Win 11 Pro/Education相当、CPU: N4500以上、ストレージ: 64GB以上、メモリ: 8GB(4GB許容)など |
| Google Chrome OS (Chromebook) | Googleのサービスとの相性バツグンで、セキュリティもしっかり | 設定が簡単で比較的安い。電池も長持ち | 使えるソフトがWindowsやiPadより少ない場合がある | OS: Chrome OS、CPU: N4500以上、ストレージ: 32GB以上、メモリ: 4GB以上など |
| iPadOS (iPad) | 触って操作するのが簡単で、持ち運びも楽々。創作活動向き | カメラがきれいで、アプリも豊富。電池も長持ち | キーボードを別で買う必要があるかも。少し高くつく可能性あり | OS: iPadOS、ストレージ: 64GB以上、無線: 802.11a/b/g/n/ac以上、スタンド必須など |
各OSの価格、操作性、バッテリー性能、拡張性の詳細比較
お財布に優しいのはChrome OSで、3万円台から選べます。
Windowsは選択肢が豊富で、4万円台から10万円を超える機種まで幅広く揃っています。
iPadOSは本体にキーボードやApple Pencilなどを加えると、一番高額になる傾向があります。
使いやすさでは、iPadOSが断トツ。小学校低学年の子どもでも、あっという間に使えるようになります。

Chrome OSはシンプルで分かりやすく、Windowsは機能が豊富な分、慣れるまでに少し時間がかかるかもしれません。
電池の持ちは、Chrome OSとiPadOSが優秀で8時間以上持続。Windowsは機種によって6時間から10時間とバラつきがあります。
将来的にいろんなソフトや機器を使いたいなら、Windowsが一番柔軟性があります。
Chrome OSはWebベースのアプリが中心で、iPadOSは専用アプリが充実していますが、ファイル管理の自由度はやや制限されます。

GIGAスクール構想でのおすすめOSと選定のポイント
将来のIT人材育成や汎用性を考えるなら、Windowsがおすすめです。
プログラミング教育や高校での専門的な学習にも対応でき、社会に出てからも役立つスキルが身につきます。
全国での導入実績も豊富で、参考になる情報もたくさんあるんです。
次に、コストを抑えて管理を楽にしたいなら、Chrome OSが最適です。Googleのサービスと連携しやすく、クラウド中心の学習環境が簡単に作れます。
セキュリティ面でも自動更新機能があるので、管理者の手間が大幅に省けるでしょう。
そして直感的な操作性と創造的な学習を重視するなら、iPadOSがぴったり。
特に美術や音楽などの芸術系の授業では威力を発揮し、子どもたちの創造性を引き出してくれます。
ただし、予算に余裕がある学校での導入が現実的でしょう。

授業や校務を効率化するおすすめICTツール7選
ここからは、実際の教育現場で大活躍しているICTツールを7つご紹介します。
どれも、学習意欲の向上や情報活用能力の育成、先生方の業務効率化に実績のあるツールばかりです。
資料作成・共有:Googleスライド
Googleスライドは、みんなでプレゼン資料を作るのにとっても便利なツールです。一番の魅力は、複数の人が同時に同じ資料を編集できること。
例えば古典の授業で、グループごとに和歌について調べて発表するとします。
従来なら一人が作って他のメンバーが見るだけでしたが、Googleスライドなら全員が同時に資料作りに参加できます。
Aさんが背景を調べている間に、Bさんは作者について、Cさんは現代語訳を担当するといった具合に、効率よく作業が進みます。
先生も生徒たちの作業をリアルタイムで確認できるので、「この班はちょっと困っているな」「この班はすごく順調だな」といったことがすぐに分かります。
オフラインでも対応してるため、インターネットがつながらない時でも作業できて、つながった時に自動で同期される点も便利です。
板書デジタル化:Adobe Scan
「せっかくICT機器があるのに、板書はアナログのまま?」という課題を解決してくれるのがAdobe Scanです。
ホワイトボードや黒板に書いた内容を、スマホやタブレットで撮影するだけで、きれいなデジタル資料に変換してくれます。
撮影すると自動的に補正されて、文字がはっきり読める状態でPDF化されます。これなら、いつもの板書スタイルを変えずに、ICT化の恩恵を受けられますね。
欠席した生徒への資料提供もすぐにできますし、手書きの課題や実験レポートの管理にも活用できます。特に数学の複雑な計算過程や理科の図表など、手書きの良さを活かしながらデジタルの便利さも享受できる優れものです。
https://www.adobe.com/jp/acrobat/mobile/scanner-app.html
動画授業作成:Lecta
「動画で授業を作りたいけれど、編集が大変そう…」という先生方の強い味方がLectaです。自動カメラワーク機能で、先生の動きに合わせて最適なアングルで撮影し、編集作業を大幅に簡単にしてくれます。
反転授業や個別最適な学習で威力を発揮します。生徒は自分のペースで動画を見て、分からないところは何度でも繰り返し確認できます。「先生、もう一回説明して」と言われても、「動画で確認してね」と言えるので、先生の負担も軽くなります。
保護者向けの授業参観動画を作って、普段見ることのできない授業の様子を共有することもできます。
https://lecta.products.splyza.com
AI型学習教材:すらら
「すらら」は、一人ひとりの理解度に合わせて問題を自動で作ってくれるAI教材です。生徒が間違えた問題を分析して、「ここでつまずいているから、こっちから学習し直そう」と提案してくれます。
例えば、中学生の数学で分数の計算ができない生徒がいたとします。普通なら「分数の計算を練習しなさい」で終わりですが、すららは「小学4年生の約分から復習しましょう」といった具合に、根本的な理解不足を見つけて対処してくれます。
先生は生徒一人ひとりの学習状況をリアルタイムで把握できるので、「この子はここで困っている」「この子はもう少し発展問題をやっても大丈夫」といった個別指導が効率的に行えます。
オンライン辞書・参考書:ジャパンナレッジSchool
「図書室に行かなくても、いい辞書や参考書が使えたらなあ」という願いを叶えてくれるのが、ジャパンナレッジSchoolです。国語辞典、英和・和英辞典、百科事典、文学作品など、学習に必要な資料がオンラインで一括検索できます。
教室でも家でも同じ質の高い資料にアクセスできるので、調べ学習や課題研究の幅がぐっと広がります。複数の辞書を横断検索できるので、「この言葉の意味をもっと詳しく知りたい」という時に、効率よく情報収集できます。
信頼できる情報源なので、インターネット検索で出てきた怪しい情報に惑わされる心配もありません。
https://school.japanknowledge.com
課題管理:Google Classroom
課題を出して、回収して、チェックして、返却して…という一連の流れを、すべてデジタルで管理できるのがGoogle Classroomです。
先生は課題の進捗状況をリアルタイムで確認できるので、「この子はまだ手をつけていない」「この子はもう提出している」といったことが一目瞭然。提出期限が近づくと自動で生徒にお知らせしてくれるので、うっかり忘れを防ぐこともできます。
写真や動画、音声など、いろんな形式の課題に対応していて、保護者にも学習状況を共有できる機能があります。
https://sites.google.com/view/classrooms-workspace
オンラインコミュニケーション:Google Meet
遠隔授業はもちろん、グループワークや保護者面談など、いろんな場面で活用できるのがGoogle Meetです。画面共有機能で教材を見せたり、生徒の発表を効率よく行ったりできます。
チャット機能もあるので、声だけでは伝えにくいことも補完できます。録画機能を使えば、欠席した生徒への授業提供や復習用教材として活用することも可能です。
ブレイクアウトルーム機能で、クラス全体を小グループに分けて議論させることもできるので、従来の一方向的な授業から、生徒が主体的に参加する授業へと変革できます。
ICT教育導入におけるデメリットと対策
ICT教育には素晴らしいメリットがたくさんありますが、気をつけなければならない点もあります。これらをしっかり理解して、適切な対策を立てることが大切です。
インターネット利用と情報モラルの問題
インターネット環境が整うということは、良い情報にアクセスしやすくなる一方で、有害な情報に触れるリスクも高まるということです。長時間の利用によるネット依存症や、SNSでのトラブル、個人情報の扱いなど、情報社会特有の問題も心配されます。
でも、これらの問題は技術と教育の両面から対策できます。フィルタリングソフトで有害サイトをブロックしたり、利用時間を制限したりといった技術的な対策と同時に、情報モラル教育をしっかり行うことが重要です。
「なぜこの情報は信用できないのか」「どうして個人情報を守る必要があるのか」といったことを、子どもたち自身が理解できるように指導していきます。デジタル・シティズンシップ教育という考え方も注目されていて、デジタル社会の良き市民として行動できる能力を育てることも大切です。

思考力・表現力・書く力の低下への対策
「検索すればすぐに答えが見つかるから、深く考えなくなるのでは?」「手書きの機会が減って、漢字が書けなくなるのでは?」という心配もありますね。
確かにそういう面もありますが、ICTの使い方次第で解決できます。検索する時は複数の情報源を比較検討させたり、「なぜそう思うのか」を考えさせたりして、批判的思考力を鍛えることができます。
手書きとデジタルの使い分けも重要です。タブレットに直接書き込める機能を活用すれば、手書きの良さを残しながらデジタルの便利さも享受できます。思考の過程を可視化するマインドマップや、論理的な文章構成を支援するアウトライン機能も効果的です。
定期的に手書きの課題も取り入れて、バランスの取れた学習環境を維持することが大切です。
長時間利用による健康面への配慮
長時間画面を見続けることで起こる眼精疲労や肩こり、頭痛などの健康問題も無視できません。特に成長期の子どもたちにとって、これらの影響は深刻になる可能性があります。
適切な使用時間制限を設けて、定期的に休憩を取る習慣をつけさせることが大切です。ブルーライト対策として画面の明度を調整したり、ブルーライトカット機能を活用したりすることも効果的です。
正しい姿勢で使うことも重要です。机や椅子の高さを調整し、画面との適切な距離を保つように指導します。ICT機器を使わない時間も意識的に設けて、外で遊んだり本を読んだりする時間とのバランスを保つことが必要です。
家庭でも同じように配慮してもらえるよう、保護者との連携も欠かせません。
【導入事例】ICT機器活用で変わる学校の学びと教員の働き方
実際にICT機器をうまく導入して、大きな成果を上げている学校の事例をご紹介しましょう。
東京都内のA小学校では、Chrome OSを全校に導入し、Google Classroomを中心とした学習環境を作りました。導入前は宿題の提出率が70%程度だったのが、デジタル化によって95%まで向上しました。
子どもたちは家でも学校と同じ環境で勉強できるようになり、先生は誰がいつ宿題を出したかリアルタイムで把握できます。「まだ提出していない生徒には個別に声をかけよう」といったきめ細かい指導が可能になりました。
AI型学習教材「すらら」を使うことで、一人ひとりの理解度に応じた問題が自動で出題されるようになり、つまずきポイントも正確に把握できるように。その結果、全国学力テストの平均点が15%も向上し、何より子どもたちの学習意欲が目に見えて向上しました。
先生方の働き方も大きく変わりました。これまで手作業で行っていた出席管理や成績処理が自動化され、一人当たりの校務時間が週5時間も短縮されました。その分、子どもたちとの個別面談や授業準備により多くの時間をかけられるようになり、教育の質も向上しています。
保護者との連絡もデジタル化されて、緊急時の一斉連絡や個別相談も格段に効率的になりました。
まとめ
GIGAスクール構想は、単なる機器導入ではありません。教育そのものを変革する大きなチャンスなんです。
この記事でお伝えした選定ポイントを参考に、皆さんの学校の方針と予算に合ったICT機器を選んでください。きっと、子どもたちの学習意欲向上と先生方の業務効率化を同時に実現できるはずです。
大切なのは、なぜ導入するのかを明確にすること、長期的な費用を考慮すること、使いやすさとサポート体制を重視することです。Windows、Chrome OS、iPadOS、どれにも魅力がありますが、学校の状況に応じた最適解があります。
そして、ICTツールを効果的に使いこなし、起こりうるデメリットに適切に対処することで、安全で質の高いICT教育環境を作ることができます。
成功している学校の事例を見ても分かるように、適切に導入されたICT機器は、一人ひとりに合わせた学びとみんなで協力する学びの両方を実現し、情報を活用する力の育成に大きく貢献します。先生方の働き方改革にも効果的で、教育の質向上と効率化を両立させることができるのです。
分からないことがあれば、ICT教育の専門家や実績豊富な事業者に相談するのも一つの手です。
- まず、自校の教育目標とICT導入の目的をはっきりさせましょう
- 予算計画を立てて、長期的にかかる費用を計算してみましょう
- 複数のOS・機器を実際に比較して、デモンストレーションをお願いしてみましょう
- 先生方の研修計画とサポート体制を整えましょう
- 段階的な導入計画を立てて、効果を測る方法を決めましょう
皆さんの学校に最適なICT機器選びと効果的な活用で、子どもたちの可能性を最大限に引き出す教育環境を実現してください。






