GIGAスクール構想による「1人1台端末」環境の整備から数年が経過し、今、大きな転換点が訪れようとしています。
それが「GIGA第2期(NEXT GIGA)」と呼ばれる大規模な端末更新です。
なぜなら、2025年度には全国の小中学校で使われる端末の多くが更新時期を迎え、その数は900万台以上に上ると見込まれているからです。
この空前の規模の更新は、単なる機器の入れ替えに留まりません。
例えば、文部科学省は都道府県単位での「共同調達」を推進し、コスト削減や地域格差の是正を目指しています。
同時に、使い終えた端末の「適正な処分」や、高齢者支援、探究学習といった革新的な「再利用」も大きな課題となっています。
本記事では、GIGA第2期の全体像から、実務担当者が押さえるべき公式手続き、そして端末の未来を拓く再利用策まで、必須情報を網羅的に解説します。
GIGAスクール端末更新(GIGA第2期)の全体像とタイミング

GIGAスクール構想の初期に導入された端末は、多くが2024年度末から2025年度にかけて更新の時期を迎えます。
これは「GIGA第2期」または「NEXT GIGA」と呼ばれ、教育現場における次なる大きなステップと位置付けられています。
単なるハードウェアの更新ではなく、これまでの運用経験を踏まえ、より効果的なICT活用を目指す重要な機会です。
特に2025年度からは更新が集中すると予測されており、計画的な準備が不可欠です。
文部科学省の調査によれば、2025年度には全小中学校の端末の約7~8割、実に900万台以上が更新時期を迎える見込みです。
この一斉更新は「2025年度問題」とも呼ばれ、調達や予算確保、データ移行作業が短期間に集中する懸念があります。
参考:産経新聞
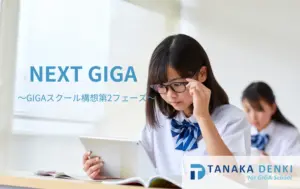
文科省が示す年度更新タスクリストとガイドライン

GIGA第2期における端末更新を円滑に進めるため、文部科学省は実務担当者向けの重要な資料を公開しています。
これらの文書は、調達計画から予算措置、実際の運用切り替えまでに必要な手続きを体系的にまとめたものです。
自治体や学校の担当者は、これらの公式ガイドラインを熟読し、計画の指針とする必要があります。
GIGAスクール構想 年度更新タスクリストの活用法
特に重要なのが「GIGAスクール構想 年度更新タスクリスト」です。
従来のコンピュータ室とは異なり、1人1台端末環境ではクラウドベースのアカウント管理やデータ移行が中心となります。
このタスクリストは、複雑な年度更新作業を「計画・準備」「実行」「確認」のフェーズに分け、必要な作業項目を時系列で示しています。
校長・教頭などの管理職や情報担当の教員は、これを用いてスケジュールを管理し、作業漏れを防ぐことが求められます。
参考:文部科学省 GIGAスクール構想 年度更新タスクリスト
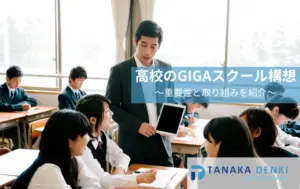
調達関連の重要文書一覧(基金、最低スペック基準など)
端末更新の予算確保と仕様決定において、以下のガイドラインは必読です。これらは調達のルールや端末に求められる性能を定義しています。
- 学習者用コンピュータ最低スペック基準があり、端末選定の基礎となる仕様書です。OSごとの推奨スペックや、バッテリー駆動時間、耐久性などが定められています。
- GIGAスクール構想加速化基金管理運営要領とは、更新にかかる費用を補助する基金の運用ルールです。補助対象となる経費や申請手続きが明記されています。
- GIGAスクール構想の下での端末利活用促進に向けた取組の方向性として、第2期におけるICT活用のビジョンが示されています。
各OS事業者が示す円滑な年度更新の概要資料
端末のOS(オペレーティングシステム)を提供する主要3社も、年度更新を支援する資料を公開しています。
- Apple (iOS/iPadOS)
- Google (ChromeOS)
- Microsoft (Windows)
これらの資料には、各OSの管理コンソール(MDMなど)を使った具体的なアカウント移行手順やデータバックアップの方法が解説されています。
自校で採用しているOS事業者の最新情報を確認し、スムーズな移行計画を立てることが重要です。
更新端末の適正な処分と再利用
2025年度から大量に発生する使用済み端末は、単なる産業廃棄物ではありません。
これらを「宝の山」として捉え、適正な処分を行うと同時に、革新的な再利用を進める動きが活発化しています。
GIGAスクール構想で導入された端末には、まだ十分に活用できる性能が残っているものが多く、これらを社会課題の解決に役立てようという期待が高まっています。
3省庁が求める適正な再使用・再資源化の原則
端末の処分にあたっては、情報セキュリティと環境負荷に最大限配慮する必要があります。文部科学省、経済産業省、環境省は連名で「事務連絡」を発出し、自治体に対応を求めています。
重要な原則は以下の2点です。
- 個人情報漏洩の徹底防止: 端末内のデータを確実に消去すること。データ消去が困難な場合は物理的に破壊するなど、適正な処分が求められます。
- 小型家電リサイクル法に基づく処理: 法律に基づき、認定された事業者へ適切に処理を委託し、資源の再資源化(リサイクル)を徹底することです。
再利用事例①:高齢者の生活支援・認知症ケアへの転用
使用済み端末の革新的な再利用先として、高齢者支援分野が注目されています。言語聴覚士の安田氏は、タブレット端末を高齢者の見守りや服薬通知、さらには認知症患者とのコミュニケーション支援に活用する提案をしています。神戸大学などとも共同研究が進められており、端末のカメラや音声機能を活用した心理支援など、デジタル技術による新しいケアの可能性が追求されています。
再利用事例②:探究学習(都市鉱山・STEAM教育)の教材化
故障して再利用が難しい端末でさえ、貴重な教材となり得ます。リネットジャパングループは大阪市教育委員会などと連携し、使用済み端末を「都市鉱山」として捉える教育プログラムを実践しています。
都市鉱山とは、使用済みの電子機器などに含まれる貴重な金属資源(金、銀、レアメタルなど)を、鉱山に見立てた言葉です。
児童生徒が自ら端末を解体し、内部の構造を学び、資源がどのように再資源化されるかを追体験します。このプロセスは、プログラミング教育に留まらない、理科・技術・工学・芸術・数学を横断する「STEAM教育」や、SDGs達成に向けた探究学習の生きた教材となっています。
公的な再使用の事例(職員用、公民館、PTA活動など)
前述の3省庁事務連絡では、学校内や地域コミュニティでの公的な再使用(リユース)も推奨されています。これらは、新たなコストをかけずに地域のデジタル化を推進する有効な手段です。
- 校長・教頭の業務用端末
- スクールカウンセラー(SC)やスクールソーシャルワーカー(SSW)の面談・記録用
- 教員の校務用サブ端末
- 公民館でのデジタル講座用
- PTA活動や地域イベントでの貸し出し用
- 放課後児童クラブでの利用

GIGAスクール構想の推進により、すべての児童生徒が学習用の端末を活用する環境が整備されました。
しかし、配備されたICT機器を効果的に活用するには、各学校に合わせた支援が必要です。
児童生徒の習熟度に応じた学習を実現する「きめ細かい学習指導」や、クラス全体の学びを深める「協調的な学習支援」など、多様な学習ニーズに対応できるプラットフォームが求められています。
田中電気は、これらの課題解決に必要な機能を一つに集約し、教育現場の実践的な運用をサポートすることで、児童生徒が自らの力で「主体的で創造的な学び」を実現できる環境づくりを支援します。
▶︎お問い合わせ・資料請求
田中電気の学習支援ソリューション、詳細については上記リンクからお気軽にお問い合わせください。
まとめ
GIGA第2期における端末更新は、単なる機器の入れ替え作業ではありません。
これは、日本の教育DX(デジタルトランスフォーメーション)を次のステージへ進めるための重要な試金石です。
成功の鍵は、文部科学省が示すガイドラインに沿った「計画的な移行」と、都道府県単位での「共同調達」による地域格差の是正にあります。
そして同時に、膨大な数の使用済み端末を、高齢者支援やSTEAM教育といった「未来への活用」につなげられるかどうかが問われています。
教育現場、自治体、そして民間企業が知恵を出し合い、この大規模更新を乗り越え、持続可能な学びの環境を構築していく必要があります。




