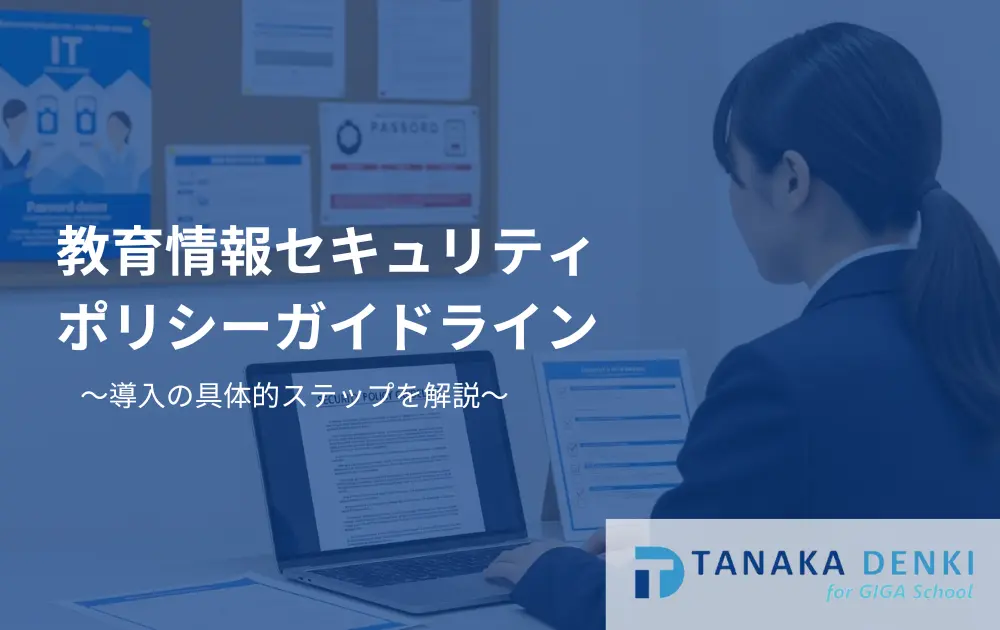教育現場におけるICT活用が急速に進む中、情報セキュリティの重要性がこれまで以上に高まっています。
文部科学省が策定した「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」は、GIGAスクール構想の推進とともに、教育現場での安全なICT活用を実現するための重要な指針となっています。
しかし、ガイドラインを理解することと、実際の運用に落とし込むことの間には大きなギャップが存在します。
特に「ネットワーク分離」から「強固なアクセス制御」への転換により、従来のセキュリティ対策では対応できない新たな課題が生まれています。
本記事では、教育情報セキュリティポリシーガイドラインの概要から、最新の運用ポイント、そして実践的な導入ステップまでを詳しく解説します。
教育委員会や学校現場の担当者が、安全で効果的な教育DXを実現するための具体的な指針を提供します。
教育情報セキュリティポリシーガイドラインとは?
ガイドラインの概要と目的
文部科学省が策定した「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」は、教職員と児童生徒が学校において安心・安全にICTを効果的に活用できる環境を整備するための指針です。
このガイドラインは、情報資産の保護、情報漏洩や改ざん、利用不能となる事態の防止を目的としており、教育現場のICT環境整備において重要な役割を果たしています。
教育現場が一般的な自治体の行政事務と決定的に異なる点は、教職員だけでなく児童生徒も日常的に情報システムにアクセスする機会があることです。
この特殊性により、一般の自治体情報セキュリティポリシーをそのまま適用するのではなく、児童生徒を含む全ての利用者を対象とした「教育情報セキュリティポリシー」の策定が教育委員会に求められています。
このガイドラインは「GIGAスクール構想」と歩調を合わせて策定・改訂されており、児童生徒一人一台端末と高速ネットワーク環境の整備を背景に、ICTを活用した個別最適な学びと協働的な学びの実現を支える重要な基盤として位置づけられています。
運用面では、単なるセキュリティ対策の羅列ではなく、教育現場の実情に即した実践的な指針を提供することで、現場の教職員が安心してICTを活用できる環境整備を目指しています。
ガイドライン改訂の背景と変遷
「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」は、ICT環境の急速な変化と新たな脅威の進化に対応するため、2017年の初版策定以降、複数回の改訂が随時行われています。
これらの改訂は、教育現場でのICT活用が拡大する中で、セキュリティと利便性のバランスを取りながら最適な運用を実現するための重要な取り組みです。
改訂の主要な背景として、2020年の新型コロナウイルス感染症の影響により、GIGAスクール構想が前倒しで実施され、急速なICT環境の普及が進んだことが挙げられます。
これにより、「クラウド・バイ・デフォルト原則」(クラウドサービスの利用を第一候補として検討する)に対応し、クラウドサービスの活用を前提としたセキュリティ対策が求められるようになりました。
最も重要な変化は、従来の「ネットワーク分離」から「強固なアクセス制御」へのセキュリティ思想の転換です。
従来の教育ネットワークは、校務系システムと学習系システムを物理的または論理的に分離する「ネットワーク分離」が主流でした。
しかし、ICTの利便性向上と教職員の働き方改革を進めるため、「強固なアクセス制御」を前提としたネットワーク統合へと方針が見直されたのです。
この転換により、従来の分離に代わり、利用者ごとのアクセス権限を適切に設定し、内部・外部からの不正アクセスを防ぐセキュリティ対策が中心となっています。
運用面では、この変更により校務用端末の持ち出し制限が緩和され、1台の端末で校務・学習系の両方を運用することが可能となり、教職員の利便性が大幅に向上しました。
「強固なアクセス制御」を中心とした最新の運用ポイント
情報資産の分類と管理の徹底
ガイドラインでは、情報資産の機密性、完全性、可用性の観点から、情報資産を4段階に分類し、管理することを推奨しています。
これにより、セキュリティ侵害時の影響度に応じた適切な管理が可能になり、限られたリソースを効率的に活用できます。
情報資産の重要性分類は以下の通りです▼
- 重要性分類Ⅰ: 情報侵害時に甚大な被害が想定され、要配慮個人情報を含むもの(例:指導要録原本、教職員の人事記録)
- 重要性分類Ⅱ: 情報侵害時に大きな被害が想定され、機密性の高いもの(例:通知表、成績、進路情報、健康診断票、システムログインID管理台帳)
- 重要性分類Ⅲ: 情報侵害時に影響を無視できないもの(例:出席簿、授業用教材、児童生徒の学習記録、職員会議資料)
- 重要性分類Ⅳ: セキュリティ侵害の影響がほとんどないもの(例:学校要覧、学校紹介パンフレット、学校ホームページ掲載情報)
運用における重要なポイントは、重要性分類Ⅱ以上の情報資産へアクセスする場合には、多要素認証を含む強固なアクセス制御による対策の遵守が求められることです。
また、情報資産の種類ごとにアクセスできる主体を限定し、職務上特に必要な場合に限り、最小限の権限(編集・閲覧・複製・ダウンロード等)を付与することが重要です。
特に児童生徒のID管理においては、進級・卒業時にもID変更を不要とすることで学習履歴を継続させる重要性が強調されています。
これにより、長期的な学習データの蓄積と分析が可能となり、個別最適な学習指導の実現に寄与します。
クラウドサービス活用におけるセキュリティ管理
クラウドサービスの利用は、学校現場のICT環境整備において有力な解決策とされていますが、その運用には適切なセキュリティ対策が必要です。
クラウド導入のメリットとして、初期費用抑制、セキュリティ水準向上(専門事業者への委任)、技術革新対応力向上、柔軟性、可用性・完全性の効率的確保、保守・運用稼働の削減が挙げられます。
一方で、クラウド利用における課題として、クラウド利用者(教育委員会等)とクラウド事業者間の「責任分界点」の理解が重要です。
SaaS型ではアプリケーション以下は事業者が管理するものの、ポリシーやデータ管理は利用者が引き続き担う項目となります。この責任分界点を正確に理解し、適切な役割分担を行うことが、安全なクラウド運用の基盤となります。
GIGAスクール構想で活用が進むSaaS型パブリッククラウドサービスは、インターネット接続が前提となるため、常にサイバー脅威に晒されるリスクがあります。このため、利用者認証情報の漏洩による「なりすまし」のリスクに特に注意が必要です。
クラウド事業者の選定においては、安全性と信頼性を優先的に確認することが推奨されています。具体的な確認事項として、以下が挙げられます。
- 第三者認証制度の取得有無(ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018, 米国FedRAMP, AICPA SOC2/3, ISMAPなど)
- 提供される監査報告書等の内容
- クラウド事業者の管理体制、守秘義務、目的外利用の禁止、データ廃棄手順、準拠法令、紛争管轄裁判所に関する契約条項
また、教育委員会や学校が管理・利用を承認していない私物端末、ソフトウェア、クラウドサービスの利用(シャドーIT)は、情報漏洩や不正アクセスのリスクがあるため、原則的に禁止されています。
特に、個人向けのWebサービスなど、約款のみで提供条件が不明確なサービスについては、利用範囲を制限し、適切なセキュリティ対策を講じる必要があります。
端末・ID管理とアクセス制御が必要
「強固なアクセス制御」を実現するためには、利用者認証、端末認証、アクセス経路の監視・制御を組み合わせた多層的なセキュリティ対策が必要です。
これらの要素が相互に連携することで、従来のネットワーク分離と同等以上のセキュリティレベルを実現できます。
利用者認証では、IDとパスワードによる認証に加え、異なる認証方式を2種類以上組み合わせる多要素認証(MFA)の利用が推奨されます。
認証要素には、知識認証(ID/パスワード)、生体認証(指紋、顔など)、物理認証(ICカード、USBトークンなど)があります。電子証明書は、多要素認証の2要素(端末認証と利用者認証の一部)を満たすことが可能な有効な選択肢です。
児童生徒への多要素認証導入については、パスワードの秘匿管理徹底などによりIDとパスワード認証を許容するものの、以下の理由から多要素認証の導入が推奨されています:
- 複雑なパスワードの記憶・管理が困難
- アカウントロック時における教職員の運用負担増
- 児童生徒による「なりすまし」の不正アクセスが既に発生している
端末認証においては、ネットワークへの不正な機器の接続を防止するため、電子証明書による端末認証を利用し、許可された端末のみのアクセスを制限することが有効です。利用者ごとのアクセス権限を適切に設定し、内部・外部からの不正アクセスを防御することで、セキュリティレベルを向上させることができます。
複数のシステムやアプリケーションで個別の認証情報管理が煩雑になるため、シングルサインオン(SSO)を導入し、一度の認証で複数のサービスにアクセスできるようにすることが運用効率化に繋がります。
MDM(モバイルデバイス管理)による一元管理も重要な要素です。教職員や児童生徒に配布された端末のセキュリティ設定、OSやソフトウェアのアップデート、アプリケーションのインストール、利用履歴の確認などを、離れた場所から一元管理できるMDMの導入が推奨されています。端末の紛失・盗難時には、遠隔でロックやデータ消去を行う機能も重要です。
マルウェア対策については、OSに標準搭載のウイルス対策ソフトの活用や、次世代型アンチウイルス(NGAV)の導入が有効です。従来のパターンファイルによる検知に加え、不審なプログラムの挙動を検知する「ふるまい検知」の活用も重要です。さらに、防御しきれなかった脅威に対し、時系列での不正なふるまいの状況を一元的に把握できるEDR(Endpoint Detection and Response)も有効なソリューションです。
Webフィルタリングと検索エンジンのセーフサーチについては、児童生徒が不適切なウェブページを閲覧することを防止するため、特定のURLやカテゴリを制限するWebフィルタリング、不適切な情報を検索結果から除外する検索エンジンのセーフサーチ、不正サイトへの接続時に警告を表示するセーフブラウジングの実装が推奨されています。
校務用端末の持ち出しルールについては、ネットワーク分離型では端末の持ち出しは原則禁止でしたが、情報セキュリティ管理者の許可を得て必要最小限の範囲で可能とされていました。
一方、強固なアクセス制御型では、アクセス制御により安全性が担保できれば、学校外への持ち出しを一律に禁止せず、1台の端末で校務・学習系の両方を運用することが可能とされています。
人的・組織的セキュリティとインシデント対応
情報セキュリティ対策は技術的な側面だけでなく、人や組織の側面からの対策も不可欠です。特に教育現場では、多様な利用者が存在するため、人的・組織的セキュリティの重要性が高まっています。
教職員の情報セキュリティ意識醸成と研修の実施は、セキュリティ運用の基盤となります。研修等を通じて、教職員の情報セキュリティに関する意識を高めることが求められており、新たな脅威や法的要件に応じて研修内容を継続的に更新し、全ての教職員が最低年1回は研修を受講することが望ましいとされています。
情報セキュリティインシデント(事故や予期せぬ事象)が発生した場合に備え、迅速な連絡、証拠保全、被害拡大防止、復旧のための緊急時対応計画(ERP)を策定し、報告体制を確立する必要があります。インシデント対応は時間との勝負であるため、事前の準備と訓練が重要です。
外部委託におけるセキュリティ確保についても、情報システムの運用や保守を外部委託する場合、情報漏洩を防ぐため、情報セキュリティが確保できる外部委託事業者を選定し、契約で守秘義務や再委託に関する制限、監査権限などを明確に定める必要があります。選定時には、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格認証取得状況などを参考にすることが推奨されます。
継続的な運用と見直しのため、情報セキュリティ対策の有効性を維持するには、定期的な自己点検と監査が求められます。監査結果は、情報セキュリティポリシーや関連規程の見直しに活用され、PDCAサイクルによる継続的な改善に繋がります。
教育情報セキュリティポリシー運用のための具体的なステップと支援
運用のためのロードマップ
教育情報セキュリティポリシーの実効性を高めるためには、段階的かつ継続的な取り組みが重要です。
効果的な運用を実現するためのロードマップとして、以下のステップが推奨されています。
自治体のICT環境や学校の実情をヒアリングし、情報資産の棚卸しを行うことで、現状と課題を明確にします。この段階では、既存のシステム構成、利用状況、セキュリティ対策の実施状況を詳細に調査し、ガイドラインとの差異を把握することが重要です。
文部科学省のガイドラインに沿って、基本方針、対策基準、実施手順の骨子から案を作成し、関係者との合意形成を図りながら完成させます。この過程では、各自治体の特性や学校現場の実情を踏まえた現実的なポリシー策定が求められます。
策定したポリシーを各学校の運用ルールである「実施手順」に具体的に落とし込み、教職員が内容を理解し、行動に移せるようワークショップや研修を通じて浸透させます。この段階では、理論的な知識だけでなく、日常業務での実践的な活用方法を含めた指導が重要です。
情報セキュリティは一度対策を講じたら終わりではなく、常に変化する脅威に対応するため、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Act)のサイクルを回し、セキュリティレベルを少しずつ高めていく必要があります。
専門業者やソリューションの活用
教育委員会や学校現場にはICTや情報セキュリティの専門家が不足していることが多いため、専門業者やソリューションを活用することが有効です。
専門的な知識と経験を持つ外部パートナーとの連携により、効率的かつ効果的なセキュリティ運用が実現できます。

外部専門家による支援のメリットとして、専門性の高い知識と経験に基づいた、ポリシー策定・更新支援、教職員向け研修や「実施手順」作成ワークショップの提供があります。
自治体の課題を深く理解し、真摯に対応できるパートナーの選定が重要です。
2024年度までは、文部科学省の「GIGAスクール運営支援センター事業」の整備支援として、民間事業者への業務委託費用の一部に補助金が交付されるため、この機会を活用することが推奨されます。
ガイドラインに適合するための具体的なソリューションとして、以下のような選択肢があります。
| ソリューション | 概要 | 主な効果 |
| 電子証明書 | 端末認証や多要素認証に活用 | 許可された端末からのアクセスのみを許可 |
| ファイル暗号化 | 端末に保存されたファイルや持ち出し情報を自動暗号化 | 情報漏洩リスクの低減 |
| Webフィルタリング | 不適切なウェブサイトへのアクセスを制限 | マルウェア感染や不適切な情報への接触を防止 |
| ID認証サービス | クラウドサービスの認証を一括管理 | シングルサインオンの実現 |
| マネージド型クラウドサービス | 専門スタッフによる環境構築から運用までを委託 | 運用負担の軽減 |
| WAF | 公開Webサービスへの攻撃を防御 | Webアプリケーションの保護 |
| NGAV/EDR | 複雑化・巧妙化するマルウェア攻撃を検知・防御 | インシデント対応の支援 |
| SOCサービス | セキュリティ運用の専門業者に監視・対応を外部委託 | 24時間体制での監視・対応 |
これらのソリューションを組み合わせることで、教育現場の特性に応じたセキュリティ対策が実現できます。
まとめ
「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」は、単にセキュリティリスクから教育現場を守るだけでなく、ICTを安心して活用できる環境を整備することで、子どもたちの発達と学びをより豊かなものにすることを真の目的としています。この理念を実現するためには、セキュリティと利便性のバランスを適切に取りながら、継続的な改善に取り組むことが不可欠です。
教育現場のICT環境は日々変化しており、それに合わせたシステムの見直し、運用ルールの変更、新たな課題への対応が求められます。安全性、学習機会の保障、ネットワークの可用性という3つの要素のバランスを適切に調整することで、効果的な教育環境の実現が可能となります。
各教育委員会は、現状を踏まえた上で、ガイドラインの理念を理解し、「あるべき姿のグラウンドデザイン」を先行して考える意識の改革が不可欠です。これは、単なるセキュリティ対策の実装ではなく、教育DXを通じて子どもたちの学びを変革するという大きな目標に向けた戦略的な取り組みとして位置づけられるべきです。
そのためには、業界の背景やサイバーセキュリティ動向を把握したパートナー企業を見つけ、協力体制を構築することが重要です。外部専門家の知見を活用しながら、教育現場の実情に即した実践的なセキュリティ運用を実現することで、安全で効果的な教育DXの推進が可能となります。
今後も技術の進歩と脅威の変化に対応しながら、教育現場が安心してICTを活用できる環境を継続的に整備していくことが、未来の教育を支える重要な基盤となるでしょう。