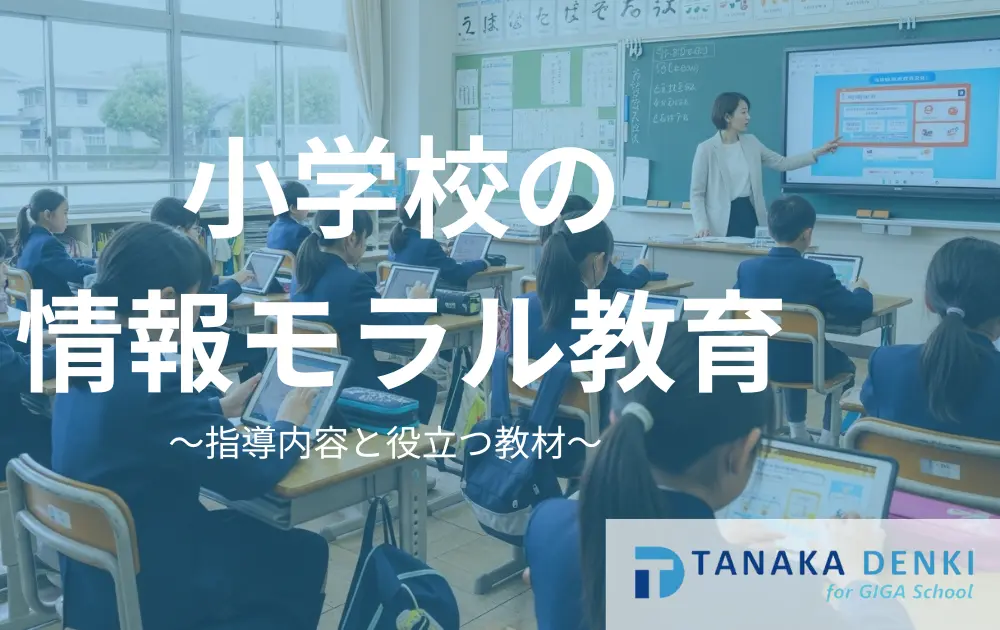小学校での情報モラル教育は、今や非常に重要です。GIGAスクール構想により、児童生徒がICTを活用する機会が急速に増えました。
この変化に伴い、インターネットの利便性だけでなく、危険性も学ぶ必要が出てきたのです。
情報モラル教育とは、情報社会で適切に活動するための考え方や態度を育むことです。
当記事では、小学校で教えるべき情報モラルの具体的な指導内容や、文部科学省などが提供する授業に活用できる教材について、詳しく解説します。
情報モラル教育とは?小学校で求められる目標と背景
情報モラル教育は、現代の小学生にとって不可欠な学習です。
文部科学省は、情報モラルを「情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度」と定義しています。
これは、情報を正しく安全に使いこなし、責任を持って行動するための土台となります。
GIGAスクール構想の推進により、1人1台の端末が配備されました。児童生徒が日常的にインターネットやICT活用を行う環境が整ったのです。
この背景から、情報モラル教育の目標は、単に機器の使い方を学ぶことではありません。
インターネットの便利さ(光の部分)と、それに伴う危険性(影の部分)の両方を深く理解することが求められています。
情報モラル教育の柱は「5つ」
情報モラル教育は、複雑に見えますが、主に5つの柱で構成されています。これらの要素をバランスよく指導することが大切です。
- 1. 情報社会の倫理
他者への影響を考え、人権や知的財産権を尊重する態度を養います。 - 2. 法の理解と遵守
情報社会に関連する法律やルール・マナーを知り、それを守る重要性を学びます。 - 3. 安全への知恵
情報社会に潜む危険(個人情報の流出、ネット依存など)を回避する方法を学びます。 - 4. 情報セキュリティ
ウイルス対策やパスワード管理など、情報を安全に守るための技能を身につけます。 - 5. 公共的なネットワーク社会の構築
情報社会の一員として、より良い社会づくりに貢献する態度を育てます。
これらは、子どもたちがデジタル・シティズンシップ(良きデジタル市民であること)を身につけるための基盤となります。

小学校における情報モラル教育の学年別指導内容
小学校の学習指導要領では、情報モラル教育は特定の教科で完結するものではありません。
道徳や総合的な学習の時間、各教科の中で、児童生徒の発達段階(年代別)に応じて指導することとされています。
文部科学省が示すモデルカリキュラムでは、年代別に指導すべきテーマが整理されています。
ここでは、低学年、中学年、高学年に分けて、主な指導内容を表で紹介します。
小学校1~2年生(低学年)の指導テーマ
低学年では、まず基本的なルール・マナーを身につけることが中心です。
| 領域 | 主な指導テーマ例 |
| 心を磨く領域 | ・約束や決まりを守って使う(利用時間、場所) ・相手が気持ちよくなる言葉を使う |
| 知恵を磨く領域 | ・大人の人と一緒に使う ・知らない人や危ない情報に近づかない |
小学校3~4年生(中学年)の指導テーマ
中学年になると、自分と他人の情報の違いを意識し始めます。
| 領域 | 主な指導テーマ例 |
| 心を磨く領域 | ・自分の情報や他人の情報を大切にする(個人情報) ・相手の立場を考えてやり取りする |
| 知恵を磨く領域 | ・協力し合ってネットワークを使う ・健康に気をつけて使う(利用時間、姿勢) |
小学校5~6年生(高学年)の指導テーマ
高学年では、より社会的な視点や情報の真偽を見極める力が求められます。
| 領域 | 主な指導テーマ例 |
| 心を磨く領域 | ・自他の権利を尊重する(著作権、肖像権) ・コミュニティでの自分の発言に責任を持つ |
| 知恵を磨く領域 | ・情報の正確さを判断する方法を知る ・契約やお金に関わる行動の意味を理解する |
小学校での情報モラル指導に役立つ教材・資料
情報モラル教育の指導にあたり、教員が活用できる公的な教材や資料は豊富にあります。
これらを活用することで、授業準備の負担を減らし、効果的な指導が可能になります。
文部科学省提供の指導資料
文部科学省は、情報モラル教育を推進するためのポータルサイトを開設しています。ここには、授業ですぐに使える資料が集約されています。
- 情報モラル教育ポータルサイト
指導手引きや事例集、カリキュラム表などがまとめられています。 - 児童生徒向けの動画教材
アニメーションなどを使い、インターネットの危険性を分かりやすく伝えます。 - 教員向けの指導手引き・ワークシート
具体的な授業の進め方や、児童生徒が考えるためのワークシートが提供されています。
これらの資料は、学習指導要領の改訂(令和元年度以降)にも対応しています。
総務省・自治体が提供する教材例
文部科学省以外も、GIGAスクール構想に対応した教材を提供しています。
- 総務省「ネット&SNSよりよくつかって未来をつくろう」
SNSの適切な使い方を中心に、動画や教材キットを提供しています。 - 地方自治体の教材(例:大分県 GIGAワークブック)
各自治体が、地域の実情に合わせて作成した独自の教材も参考になります。
保護者向けの啓発資料も活用する
情報モラルは、学校だけで完結するものではありません。
家庭との連携が不可欠です。
文部科学省は、保護者向けの動画教材やパンフレットも用意しています。
これらを活用し、保護者会などで家庭でのルール作りの重要性を伝えることも、教員の大切な役割です。
授業実践を成功させるための具体的な工夫と注意点
情報モラル教育を「やって終わり」の形式的なものにしないためには、工夫が必要です。
児童生徒が自分事として捉え、主体的に学べるような働きかけが求められます。
教員が陥りがちな課題と、その対策を紹介します。
低学年指導のポイント
低学年には、抽象的な「危険」は伝わりにくいです。具体的なシナリオを用いて指導することが効果的です。
例えば、「ゲームで知り合った知らない人から『名前を教えて』と言われたらどうするか」といった事例集を活用します。
大切なのは、「少しでも『変だな』『怖いな』と思ったら、すぐに大人に相談する」という行動を徹底することです。
これが「安全への知恵」の第一歩となります。ルールは複雑にせず、「お家の人と決めた時間だけ」「困ったらすぐ言う」など、シンプルにすることが定着のコツです。
高学年指導のポイント
高学年になると、情報を発信する機会も増えます。ここで重要になるのが、情報の信頼性(フェイクニュースの見抜き方)や、著作権・肖像権の扱いです。
「ネットの情報は全てが正しいわけではない」ことを前提に、発信元は誰か、他の情報と比べてどうか、などを確認する習慣をつけさせます。
また、著作権については、「他人が作ったものを無断で使ってはいけない」という基本を、具体的な事例(好きなアニメの画像をSNSアイコンにするなど)で指導することが大切です。
情報モラル教育の充実がICT教材活用を促進する
情報モラル教育は、児童をインターネットの脅威から守る「守り」の教育であると同時に、ICT活用の可能性を広げる「攻め」の教育でもあります。情報社会で正しく行動するための考え方と態度を身につけることで、子どもたちは初めて、端末を安全かつ効果的な学習ツールとして使いこなせるようになります。小学校段階からの体系的な指導が、GIGAスクール構想の成功の鍵を握っているのです。

GIGAスクール構想の推進により、すべての児童生徒が学習用の端末を活用する環境が整備されました。
しかし、配備されたICT機器を効果的に活用するには、各学校に合わせた支援が必要です。
児童生徒の習熟度に応じた学習を実現する「きめ細かい学習指導」や、クラス全体の学びを深める「協調的な学習支援」など、多様な学習ニーズに対応できるプラットフォームが求められています。
田中電気は、これらの課題解決に必要な機能を一つに集約し、教育現場の実践的な運用をサポートすることで、児童生徒が自らの力で「主体的で創造的な学び」を実現できる環境づくりを支援します。
▶︎お問い合わせ・資料請求
田中電気の学習支援ソリューション、詳細については上記リンクからお気軽にお問い合わせください。