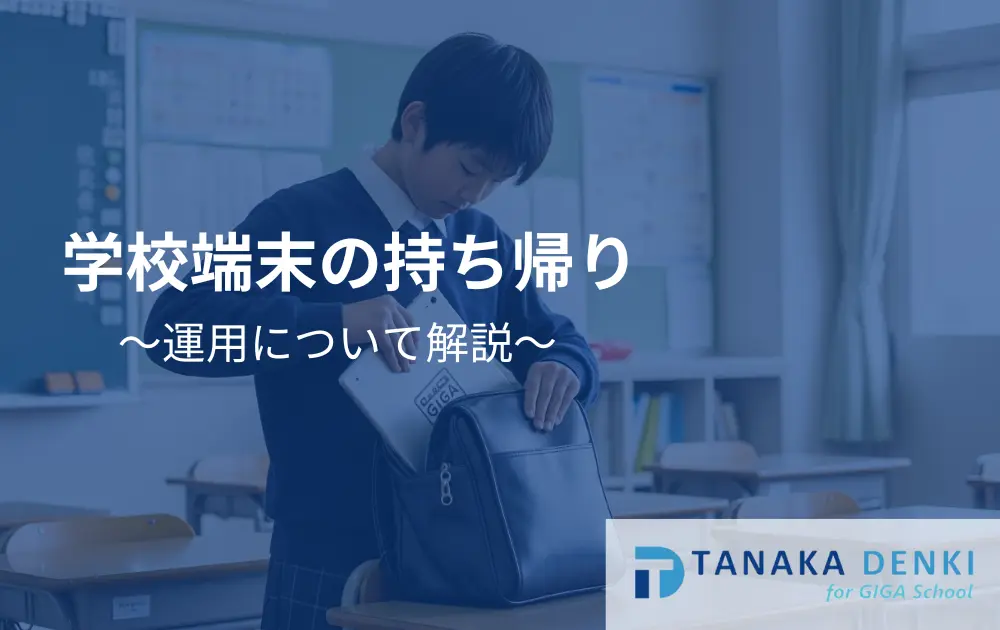GIGAスクール構想により1人1台の端末が配布されたものの、家庭での活用に課題を抱えている学校は少なくありません。
「端末を持ち帰らせたいが、トラブルが心配」「保護者の理解を得るにはどうすればよいか」「セキュリティ対策は十分だろうか」といった悩みを抱える教育関係者の声をよく耳にします。
文部科学省の調査によると、端末の持ち帰りを実施している学校は全体の約4分の1にとどまり、家庭学習での活用はさらに限定的です。
しかし、子供たちの主体的な学びを促進し、デジタル社会を生き抜く力を育むためには、家庭でのICT活用は避けて通れない課題となっています。
本記事では、GIGA端末の家庭持ち帰りを安全かつ効果的に実施するための具体的な方法、必要な準備、ルール設定のポイント、そして発生しうる課題への対応策について、実践事例を交えながら詳しく解説します。
GIGA端末の持ち帰りの必要性
GIGAスクール構想における端末活用の重要性
これからの社会を生き抜く子供たちにとって、自ら考え、自分で決めた方法や内容で学習を深める「主体的な学び」が求められています。
GIGAスクール構想で整備された1人1台の情報端末は、この主体的な学びを支援する重要なツールとして位置づけられており、学校だけでなく家庭での積極的な活用が期待されています。
従来の一斉授業中心の学習から、子供たち一人ひとりの個性や学習進度に合わせた個別最適化された学習への転換において、ICT端末の家庭持ち帰りは欠かせない要素となっています。
家庭学習でのICT活用が進まない現状
しかし、現実は理想とはかけ離れた状況にあります。2021年度の文部科学省の調査では、家庭で情報端末が十分活用されているとは言えない状況が明らかになっています。
児童生徒1人1台の情報端末の持ち帰りを実施している自治体や学校は全体の4分の1程度にとどまり、家庭での学習に活用している割合も極めて低い状況です。
さらに深刻なのは、OECDの調査結果です。日本の子供たちは海外と比較して、家庭での余暇におけるICT活用(ゲームや動画視聴など)の割合は高いものの、学習に必要な情報の検索やまとめといった学習でのICT活用頻度は極めて低いという結果が出ています。
この現状は、情報端末が授業の学習場面で活用されていても、家庭や地域での「日常の学習ツール」として定着していないことを示しています。
つまり、端末は配布されたものの、真の意味での活用には至っていないのが実情です。
これからの持ち帰り学習が目指すもの
今後期待される持ち帰り学習は、これまでの取り組みと大きく異なる2つの特徴があります。
第一に、単一の学校だけでなく、地域全体が取り組んでいくことです。家庭や地域と協力しながら、情報端末の持ち帰りを組織的・計画的に実践していく必要があります。
学校単独では限界があるため、保護者や地域コミュニティとの連携が不可欠です。
第二に、子供たちの主体的な学びにつなげることです。
従来の授業での学習課題を家庭で事前に視聴するなどの受動的な活用から、子供たちが自分で判断して情報端末を持ち帰り、学習内容や学習方法を決定するような主体的な活用が求められています。
この転換により、子供たちは単なる情報の受け手から、自ら学習をデザインし実行する主体者へと成長することが期待されます。
GIGA端末持ち帰りを円滑に進めるための準備とポイント
保護者・地域への理解促進と協力体制の構築
家庭でICT端末を有効活用するためには、家庭で活用する際の環境や条件等について、保護者や地域と共通理解を図ることが不可欠です。この共通理解なくして、持ち帰り学習の成功はありえません。
学校側は「保護者へ向けた便り」を用意し、端末の情報セキュリティ・モラル確保、学習の幅の広がり、長時間使用による健康への影響などについて保護者に理解を求める必要があります。
文部科学省が作成している「端末利用に当たっての児童生徒の健康への配慮等に関する啓発リーフレット」をベースに、学校独自のルールを加えることも有効です。
また、各家庭のWi-Fi環境を事前に把握しておくことも重要です。インターネット接続環境が整っていない家庭への配慮や、モバイルルーターの貸し出しなど、デジタルデバイドの解消に向けた取り組みも併せて検討する必要があります。
段階的な持ち帰りの実施で不安を解消
保護者の中にはICT端末の持ち帰り学習に抵抗を感じる人もいるため、本格的に持ち帰りを始める前に段階を踏んで理解を深めてもらうことが推奨されます。
まずは1日だけ持ち帰り、家庭で使ってみた感想や課題、問題点を生徒や家族からフィードバックしてもらうことから始めます。このフィードバックには、技術的な問題だけでなく、家庭での使用時間や場所、他の家族への影響なども含まれます。
学校側はそのフィードバックを元にルールを見直したり、保護者の不安点を改善したりします。その後、2日間、週末と徐々に持ち帰りの期間を長くして、本格的な持ち帰り学習へと進めていくことで、保護者の不明点や不安が解消されていきます。
この段階的なアプローチは、保護者だけでなく教師側にとっても、実際の運用上の課題を把握し、改善策を講じる貴重な機会となります。
子供たち自身がルールを考える機会を設ける
家庭に教育ICT端末を持ち帰る前に、学校で児童生徒と一緒になって家庭でのICT端末の使い方を考える時間を確保することが重要です。単に学校側が決めたルールを一方的に伝えるのではなく、子供たち自身が参加してルールを作り上げることで、より高い遵守意識を生み出すことができます。
児童生徒とともに問題点を考えることで、端末を正しく利用するという意識を高めることができます。例えば、「どのような使い方が学習に適しているか」「家族に迷惑をかけないためにはどうすればよいか」といった観点から、子供たち自身に考えさせることが大切です。
子供たちにICT端末利用のルールを守ってもらうためには、学校側の方針をきちんと理解してもらう必要があります。不適切なサイトへのアクセス禁止だけでなく、「ICT端末は学習のために使うデバイスである」という目的を説明し、子供たち自身が学習に不要なサイトかを判断できるよう促すことが大切です。
児童生徒と保護者・教師の間に信頼関係を築くことは、ルールを守ることにもつながります。見守られていると感じる子供ほど、自分の行動を省み、規則やルールから外れることにためらいを感じる傾向があることが知られています。
トラブルを未然に防ぐ!GIGA端末持ち帰り「利用ルール」作成の具体例
持ち帰り学習を安全かつ効果的に実施するためには、詳細な「持ち帰りの手引き」の作成が不可欠です。この手引きには以下の項目を含める必要があります。
目的の明確化
学校から貸し出す端末が家庭で学習活動を行うためのツールであることを明記し、学校やクラスが一時的に閉鎖した際のリモート学習や、児童生徒と教員との連絡ツールとしても活用できることを説明します。
貸出機器
児童生徒に貸し出されるGIGA端末と、持ち帰れるアクセサリ(充電用ケーブルやアダプタ)について詳細に記載し、あらかじめタブレットにインストールされているアプリ情報も提供します。

貸出期間
「令和○年○月○日~卒業時(または転出)まで」と返却時期を明記し、あくまで学校から貸与されていることを保護者と生徒に印象付けることが重要です。
健康面への配慮
健康面への配慮は特に重要な項目です。端末スクリーンとの適切な距離(例:30cm以上)、定期的な休憩(例:30分ごとに10分休憩)、就寝前の使用を控えること、部屋の明るさへの配慮などを具体的に記載します。
個人情報と情報モラル
自分や他人の名前、住所、携帯番号、アカウントなどの個人情報をインターネット上に公開しないこと、自分の端末を他人に貸し出さないこと、他の人の作品や顔写真などを勝手にインターネットに上げないこと、インターネット上の情報の真偽を見極めることの重要性を説明します。

保護者への注意喚起
GIGA端末を家庭で利用する場合の通信料や充電にかかる電気代は家庭負担となることを明記し、協力を依頼します。
また、端末の紛失・破損や情報漏洩が発生した場合の保護者の負担についても、あらかじめ明確にしておくことが重要です。
運用上の注意点と対応策
ネットワーク接続への配慮は、多くの学校が直面する課題です。GIGA端末は持ち帰っても自動的にネットワークにはつながりません。インターネットに接続するためのIDとパスワードの入力が必須となるため、詳細なマニュアル作成が必要です。
特にマンション住まいなど、多数のWi-Fiが表示される環境では、ネットワーク(Wi-Fi)がどのように表示されるか、SSIDとパスワードの違いが明確にわかるような画像付きの説明をマニュアルに含める必要があります。
充電とアップデートの管理について、学校に保管庫がなく、充電・アップデートを家庭で行うことが前提となる場合、保護者の負担が大きくなる可能性があります。前述のマニュアルを作成し、できるだけ負担を軽減する取り組みが必要です。充電器を家庭に配付し、家庭で充電しながら活用を促し、学校の授業でしっかり活用できるように進めている学校もあります。
端末の管理方法では、持ち帰りを希望者のみに貸与する場合、名簿に希望者の氏名と端末番号を記入する運用が有効です。同じ学校に学年が違う兄弟がいる場合、自分の端末ではなく兄弟の端末を持ってきてしまうケースがあるため、兄弟がいる生徒には備考欄に兄弟の分の端末番号を記載するなど、見分けられる工夫が必要です。
予期せぬ事故への対策として、「水濡れ事故」は盲点となりがちです。学校に持ち込み可能な液体が入っているもの(水筒など)には注意が必要であり、保護者の方に防水用袋に入れていただくなどの配慮をお願いするか、学校側で予算を組んでGIGA端末側を防水ケースに入れて持ち帰りができるようにするなどの対策が必要です。
GIGA端末を活用した効果的な家庭学習の実践事例
子供が自分で決める「主体的な学び」
主体的な学習につなげるためには、情報端末を持ち帰って学習する際に、子供が「自分で決める」ことが大切です。これは単なる宿題の延長ではなく、子供たち自身が学習の必要性を感じ、自ら端末を活用する意識を育むことを意味します。
石川県立金沢錦丘中学校では、家庭への端末持ち帰りを全員が同様に行うのではなく、持ち帰る生徒は保管庫の名札を変更してわかるようにすることで、子供たちの必要感に応じて持ち帰りを進め、主体的な学びにつなげています。この取り組みは、強制ではなく子供たちの自主性を尊重する姿勢を示しています。
夏休みや冬休みといった長期の休み期間に、1人1台の情報端末を家庭で活用することも効果的です。長期の休み中に、学習の内容や方法を子供が自分で決めて、自主的な学習をじっくり進めることができます。
長期休暇期間における実践例として、Web上の博物館や美術館を訪問して有名な作品や作者を調べてまとめる活動、デジタルマップやWebサイトを活用して住んでいる地域を調べる地域学習、プログラミングやタイピングを練習してICTスキルを向上させる取り組みなどがあります。
また、オンラインで休み期間の学習成果を発表し合う活動、家庭で調理に取り組んでできあがった料理や調理の過程を記録する実践的な学習、情報端末のカメラ機能を用いて家庭で録画した音楽のリコーダー演奏や体育の演技、図画工作・美術の作品などを提出する学習も効果的です。
子供たちの豊かな発想で、様々なことに試行錯誤しながら挑戦する機会として、家庭での活用に取り組ませることが重要です。
友だちとの「協働学習」の可能性
友だちと協力しながら学習に取り組むことは、子供の学習意欲の向上に大きく寄与します。長期の休みでは、一人で学習する場面が多くなりがちですが、ネットワークを経由して、お互いに協力したり教え合ったりする場面を設けることで、学習意欲が大幅に向上します。
鹿児島大学教育学部附属小学校の三宅倖平教諭は、算数で難易度のある学習課題を出し、端末を持ち帰って家庭で解かせる実践を行いました。クラウド上のチャットを用いて協力して解決してもよいとしたところ、子供同士で解き方や考え方を共有するなど、お互いに教え合うようになり、難しい算数の学習課題についても、よく分かるようになったと答える子供が増えました。
このように、情報の共有など、1人1台端末とクラウドを有効に活用することで、協働的な学びを支援することが可能となります。撮影した動画を友だちとクラウド上で共有して学び合う活動も、協働学習の効果的な形態の一つです。
一方で、チャット等の利用を制限している地域や学校もありますが、それが子供たちの主体的な学びを制限することにもつながることを十分に踏まえておくことも必要です。適切な指導のもとでの活用が、子供たちの学習効果を最大化する鍵となります。

GIGA端末のセキュリティ対策と運用管理の重要性
学校管理者による適切な運用管理
Google管理コンソールは、学校から支給されたChromebookのセキュリティ管理において非常に重要なツールです。しかし、ほとんどの学校がこの管理コンソールを毎日確認していない現状があります。
アラートセンターの確認が最も重要な機能の一つです。Google管理コンソールのアラートセンターを定期的に確認することで、不審なログインやユーザーからの迷惑メール報告の急増など、様々なアラートを一覧で確認できます。これらのアラートは日本語で表示され、不審な利用がされているかを早期に検知することが可能です。
セキュリティルールの設定では、特定の異常(例:不審なログイン)が発生した場合に、管理者だけでなく、校長先生や学年主任などにも自動でメール通知が送られるように設定できます。これにより、問題の予兆を多角的に検知し、未然に防ぐことが可能になります。
パスワードポリシーの徹底も重要な要素です。Googleアカウントには、数字の羅列や単純な単語のようなパスワードを使用すると、毎回認証が求められる機能が付いています。このようなパスワードを設定しているアカウントは、すぐに変更すべきであり、子供たちにもパスワード管理の重要性を指導する必要があります。
生徒の行動監視と情報モラル教育の連動
セキュリティソフトだけに頼るのではなく、Google管理コンソールを有効活用することで、生徒が端末をどのように利用しているか、どのツールを使っているかといった細かい挙動まで確認できます。
ただし、これは単なる監視ではありません。単に危険なサイトを規制するだけでなく、子供たちがメディアリテラシーを身につけるためには、リアルな教育と同様に、オンラインやコンピューターの適切な使い方に関する教育が不可欠です。
子供たちの活用状況を詳細に把握し、適切に支援することで、子供たちが伸び伸びと端末を活用できる環境を構築できます。これは制限や規制のための監視ではなく、子供たちの成長を支援するための見守りと捉えることが重要です。
まとめ
GIGA端末の家庭への持ち帰りは、子供たちがこれからの社会を生き抜くために必要な「主体的な学び」や「協働学習」を促進する上で不可欠なステップです。しかし、その成功には、単に端末を配布するだけでなく、綿密な準備と運用体制の構築が求められます。
特に、保護者や地域との共通理解を図り、詳細な「持ち帰りの手引き」を作成することが、トラブルを未然に防ぎ、安心安全な学習環境を確保する上で重要です。また、家庭のネットワーク環境への配慮や、充電・管理の仕組み、水濡れ事故対策など、具体的な運用上の課題にも事前に対応策を講じる必要があります。
さらに、Google管理コンソールのようなツールを活用した適切なセキュリティ対策と運用管理は、生徒の学びの状況を把握し、情報モラル教育と連携させることで、子供たちの成長を支援する上で不可欠です。
教師は「伴走者」として、子供たちの主体的な学びを支援し、GIGA端末が豊かな学習機会を創出するための重要な役割を担います。できることからスタートし、段階的に取り組みを進めることで、1人1台端末の家庭学習での有効活用を実現していきましょう。