教育現場において、教職員の長時間労働や業務の非効率性が深刻な問題となっている現在、校務DXが注目を集めています。
校務DXとは、デジタル技術を活用して学校の業務を効率化し、教育の質を向上させる取り組みのことです。
文部科学省も積極的に推進するこの変革は、単なるデジタル化にとどまらず、教育現場の根本的な改革を目指しています。
校務DXの定義
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用して業務やサービスの改善を図る取り組みを指し、校務DXはこの概念を教育現場に応用したものです。
校務DXは、単にアナログな業務をデジタルに置き換えるだけでなく、業務フローの見直しや外部連携の促進、さらにはデータ連携による新たな学習指導や学校経営の高度化を目指す、本質的な変革を意味します。従来の紙ベースの業務から脱却し、ICTを活用した効率的な校務運営を実現することで、教職員がより教育活動に専念できる環境を構築することが最終的な目標となります。
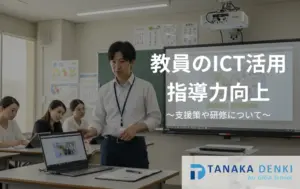
校務DXが推進されている理由
校務DXが急速に注目される背景には、複数の社会的要因があります。
急速な社会変化への対応と持続可能な教育環境の実現
社会全体のデジタル化が進む中でICTの活用が教育現場の重要な基盤と位置づけられています。
特に新型コロナウイルス感染症のようなパンデミックや少子化・人口減少が進む社会において、持続可能な教育環境を実現する必要性が高まっています。
教職員の長時間労働解消と教育の質の向上
教職員の長時間労働や業務の非効率性、地域間の学力差といった課題を解消し、教育の質を向上させるためにICTの導入と活用が有効と捉えられています。
中央教育審議会「令和の日本型学校教育答申」でも、教師の長時間勤務を解消し、学校の働き方改革を実現するために校務DXが大きな役割を果たすと位置づけられています。
GIGAスクール構想との連携
1人1台端末の整備を目指したGIGAスクール構想が推進され、学びの個別最適化や協働的学びを支える環境が整備されてきたことに伴い、校務の情報化が求められています。
この基盤を活用することで、校務DXの推進がより効果的に行える環境が整いつつあります。
校務DXを推進する主要な4つの柱と具体的な活用例
校務DXの推進には、以下の4つの柱が重要な役割を果たします。
統合型校務支援システムの活用
校務DXの中心となるシステムで、教務系(成績処理、出欠管理)、保健系(健康診断管理)、学籍系(指導要録作成)、学校事務系などを統合し、情報の一元管理と教職員の業務効率化を促進します。
従来のように各システムが独立していた状態から、一つのプラットフォームで統合的に管理できるようになることで、データの重複入力を避け、業務の効率化を図ることができます。
ICTツールの導入と日常業務の効率化
グループウェアや汎用的なクラウドサービスを導入し、小テストや欠席連絡のデジタル化など、日常業務の効率化を図ります。こ
れまで紙ベースで行っていた業務をデジタル化することで、教職員の事務負担を大幅に軽減できます。

ロケーションフリー化の実現と業務継続性の向上
校務用の情報システムをフルクラウド化し、場所を問わず業務が遂行できる環境を整備するとともに、災害や感染症流行時などの緊急時の業務継続性を向上させます。
文部科学省は2029年度までに「教職員の働き方改革にも資するロケーションフリーでの校務処理を行っている地方公共団体の割合」を100%にするという目標を掲げています。
参考資料:【資料2-2】次期ICT環境整備方針の在り方ワーキンググループ取りまとめ(案)(概要)
標準化とデータ連携による教育活動の高度化
帳票類や業務プロセスの標準化を進め、業務効率を向上させるとともに、教育データや行政データとの連携を強化し、子どもたちの支援や政策決定に活用可能なデータの利用を促進します。
統合されたデータを可視化するダッシュボードの導入も進んでおり、児童生徒の出欠状況や成績、健康状態などの情報を一元的に把握・管理できるようになっています。
校務DXのメリット
校務DXの推進により、教育現場には様々なメリットがもたらされます。
教職員の働き方改革の推進
事務作業がデジタル化されることで業務効率が向上し、例えば、統合型校務支援システムを導入した札幌市では年間1人あたり103時間、茨城県つくば市では年間89.2時間の校務時間削減が報告されています。
これにより、教員の心身の健康が保たれ、ライフワークバランスも向上すると考えられます。
リモートでの授業・校務の実現
校務DXが進んでいれば、感染症蔓延時や台風などの災害時でも、迅速に在宅での授業や校務に切り替えることが可能です。
特に、大規模災害におけるレジリエンスの観点から校務支援システムのクラウド化が重要であり、被災時でも児童生徒の安否確認や健康状態の把握、学習支援などの業務を安全に実施できるようになります。
情報共有の円滑化
デジタルプラットフォームを通じて、教員間での情報共有がリアルタイムで可能になります。
これにより、情報の一元管理や共有が進み、教員間の情報格差が減少することが期待されます。さらに、教育委員会・学校・保護者間のデータ連携も充実し、よりスムーズな情報共有が実現できます。
より効果的な教育活動の展開
手作業や紙ベースの作業をデジタル化することで、データ入力や処理の時間が短縮され、効率化によって教員が授業をより磨く時間を確保できるようになります。
また、生徒の成績、出席状況、行動記録などのデータを一元管理することで、個々の生徒の状況を総合的に把握するといった教育支援が可能になります。
文部科学省も「学校における働き方改革」の目的として、教員が子どもたちに対して効果的な教育活動を行えるようになることを掲げています。
全国の校務DX推進状況と残る課題
現在のデジタル化の進捗状況
デジタル庁が2025年2月時点で公開している『校務DXの取組に関するダッシュボード』によると、全国での校務デジタル化の進捗状況は以下のとおりです。
| 分類 | 具体的な内容 | 半分以上がデジタル化されている割合 |
| 教員と保護者間の連絡のデジタル化 | 欠席・遅刻・早退連絡 | 76% |
| お便りの配信 | 49% | |
| 調査・アンケートの実施 | 61% | |
| 教員と児童生徒間の連絡等のデジタル化 | 各種連絡事項の配信 | 28% |
| 調査・アンケートの実施 | 54% | |
| 学校内の連絡のデジタル化 | 校内での資料共有 | 76% |
| 校内での情報共有 | 77% | |
| 調査・アンケートの実施 | 67% | |
| その他 | FAXの原則廃止 | 23% |
| 押印の原則廃止 | 7% |
※2025年2月時点のデジタル庁『校務DXの取組に関するダッシュボード』のデータより
この表からもわかるように、欠席連絡や校内での情報共有は比較的進んでいるものの、FAXの廃止や押印の廃止といった根本的な業務改革はまだ途上にあります。
校務DXにおける主な課題
校務DXの推進には、いくつかの重要な課題が存在します。
働き方改革の遅れとオンプレミス型システムの制約
教職員の多くは、個人情報を扱う校務システムがオンプレミス形式で自前のサーバーに構築されているため、職員室の校務用端末からしかアクセスできません。
これにより、自宅からのテレワークなどができず、感染症や災害発生時に柔軟に校務を行うことが難しい状況です。
紙ベース業務とクラウド化の未普及
校務で使用する文書のほとんどが紙ベースであり、書類の印刷・押印・手書き修正など、業務効率が悪い現状があります。
多くの学校では、セキュリティポリシーがクラウド利用に対応していないなどの理由で、汎用的なクラウドツールを十分に活用できていません。
学習系データと校務系データの連携困難
GIGAスクール構想により学習系データの蓄積は進んでいますが、校務系のデータとの連携が進んでいないため、データを活用して教育を高度化していくことが難しい状況です。
導入コストの高さと小規模自治体の課題
校務支援システムの導入コストは非常に高く、特に小規模校を多く抱える教育委員会はコストの問題で導入に踏み切れない状況にあります。
災害時の業務継続性リスク
現状の校務支援システムが自前のサーバー上で稼働している場合、災害発生時にシステムやデータが失われると、業務の継続性が損なわれるリスクをはらんでいます。
実際に、東日本大震災では被災地域の学校の40%がデータを損失したという報告もあります。
参考:GIGAスクール構想の下での校務DXについて~教職員の働きやすさと教育活動の一層の高度化を目指して~ P7
校務DXを成功に導くための重要ポイント
GIGAスクール環境を最大限に活用する
GIGAスクール構想により、教員と児童生徒に1人1台端末やクラウドツールが貸与されているため、この環境を活かして、オンライン学習の促進や校務のデジタル化を進めることが可能です。
既存のインフラを有効活用することで、追加コストを抑えながら効率的な校務DXを推進できます。
クラウド環境を活用した校務システムの導入
多くの学校がクラウド環境を十分に活用できていない現状がありますが、通知文書の配布効率化など、クラウドを活用することで業務効率が大幅に向上します。
文部科学省も校務系・学習系ネットワークの統合や校務支援システムのクラウド化を推進しています。
業務フローの徹底的な見直しと標準化
校務DXの推進を妨げている要因として、FAXの使用や押印、必要書類の多さなどが挙げられます。これらの紙ベースの業務フローを徹底的に見直し、標準化を進めることが不可欠です。
政府も2024年6月の「デジタル行財政改革 取りまとめ2024」において、教育現場でのFAXや押印を2025年末までに原則廃止するとしています。
参考:デジタル行財政改革取りまとめ2024(案)について P1
強固なセキュリティ対策(ゼロトラストの考え方)
学校では生徒に関する多岐にわたる機密データを扱っているため、セキュリティについては特に注意を払う必要があります。
文部科学省は「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和6年1月)」を策定しており、ガイドラインに準拠したシステムの導入が推奨されています。
従来のオンプレミス型からクラウドへ移行する際には、ゼロトラストセキュリティの考え方を前提とした強固なセキュリティ構築が重要となります。
定期的なIT研修の実施と専門家への外注
ITの世界は常に変化しており、苦手意識を持つベテラン教員だけでなく、若手であっても最新のITに精通しているとは限りません。そのため、全教職員を対象とした定期的なIT研修は欠かせません。
学校で働く職員は仕事量が多いうえ、ITについて十分な知見を持っているわけではないため、安全かつ使い勝手の良いシステムの導入には、外部の専門企業に委託することが有効な選択肢となります。
校務DXの成功事例
クラウド化で働き方を変化させた自治体の事例
高岡市教育委員会では、最新の文部科学省セキュリティガイドラインに準拠した校務のクラウド化に取り組みました。
これにより、教員端末の1台化と、ロケーションフリーで校務ができる環境がほぼ実現されています。この取り組みにより、教職員の働き方に大きな変化をもたらしています。
汎用クラウドツールを活用した具体的な取り組み事例
文部科学省が紹介している事例のひとつに、練馬区立関町北小学校の取り組みがあります。この学校では、GIGAスクール構想で定められた標準仕様のソフトウェアを積極的に活用し、校務のデジタル化(DX)を推進しています。
たとえば、保護者との連絡をデジタル化するために、Googleフォームやアプリを利用した仕組みを導入しています。これにより、保護者は児童の欠席や遅刻などをオンラインで連絡できるようになり、事務職員が電話で対応する手間が大きく減りました。
また、教材フォルダのデータベース化にも取り組んでいます。教員それぞれが授業で使う教材をデータとしてフォルダに保存・管理することで、校内で教材の共有が可能になり、教材研究の効率も高まりました。
さらに、配布物や会議資料のペーパーレス化も進めています。学級通信などの配布物や会議用の資料は、複数の教員で同時に編集・作成できる環境を整備。これにより、印刷の手間を減らすだけでなく、教員一人ひとりが自分のペースで作業を進められるようになっています。
教員同士の情報共有にも工夫があります。Googleドライブを活用することで、各教員が持っている教材や資料、生徒に関する情報を簡単に共有できるようになりました。その結果、教材の準備にかかる時間が短縮されるとともに、生徒情報の共有もスムーズに行えるようになっています。
まとめ
校務DXは、教員が児童や生徒への指導業務以外の情報管理や保護者対応、学校内外の連絡調整業務などの校務負担を軽減し、より児童生徒と関わる時間を増やすために不可欠な取り組みです。
業務効率化、働き方改革の推進、リモート対応能力の向上、情報共有の円滑化といった多岐にわたるメリットをもたらします。
最終的には、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を支える教育活動の高度化を目指す基盤となります。校務DXを成功に導くためには、単にデジタルツールを導入するだけでなく、業務プロセスの見直し、教職員の意識改革、そして強固なセキュリティ対策が鍵となります。
これらの取り組みを通じて、教員が教育活動に専念できる、より質の高い未来の教育現場の実現が期待されます。校務DXは、教育現場の変革を通じて、最終的には子どもたちにとってより良い教育環境を提供することを目指しているのです。





