新型コロナウイルス感染症の流行を機に急速に普及したオンライン授業。
一時的な緊急対応から始まったこの取り組みは、今や教育の新たなスタンダードとして定着しつつあります。
国内eラーニング市場も2021年度には3,309億円を超える規模に成長し、教育のデジタル化が加速しています。
しかし、「オンライン授業とは具体的に何なのか?」「どのような種類やメリット・デメリットがあるのか?」といった疑問を抱く方も多いのではないでしょうか。
本記事では、オンライン授業の基本から導入方法、成功事例まで網羅的に解説し、時間や場所を超えた新しい学びの可能性をご紹介します。
オンライン授業とは?
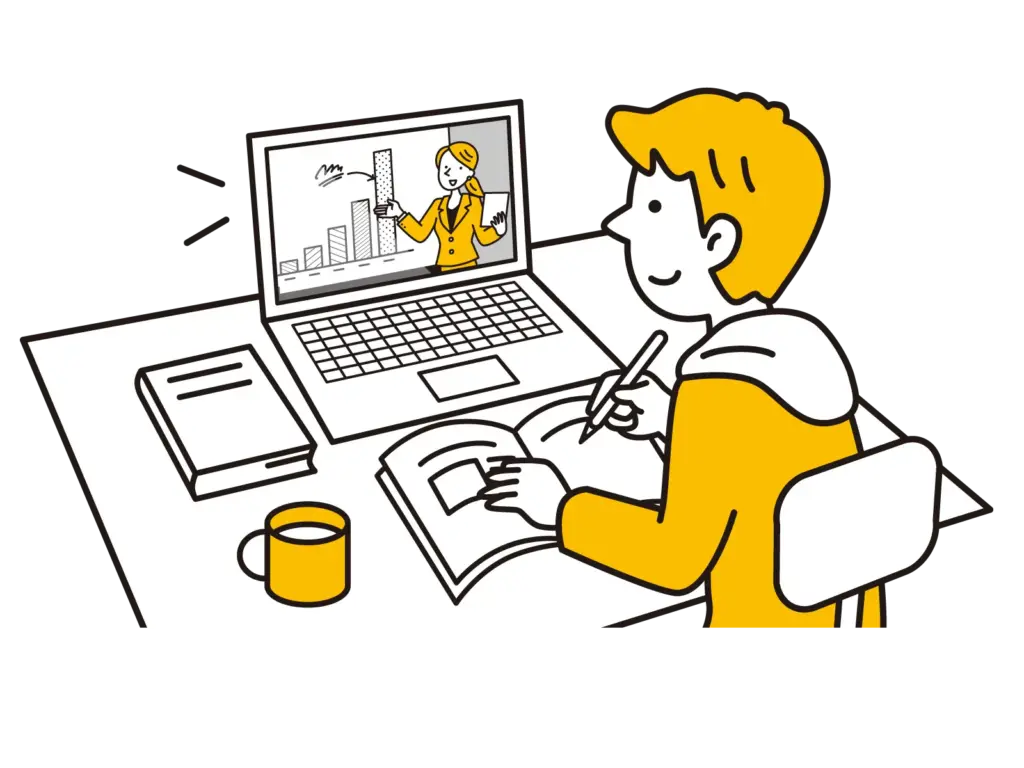
オンライン授業は、インターネットを介して行われる遠隔授業を指します。
パソコンやタブレット端末、スマートフォンなどを使用し、児童生徒は自宅などインターネットにアクセスできる場所から授業を受けることが可能です。
時間や場所にとらわれず、いつでも・どこでも・何度でも授業を受けられる点が最大の特徴となっています。
従来の通信教育が主に郵送されるテキスト教材と添削が中心であったのに対し、オンライン授業は学習者の端末に直接コンテンツが配信され、動画教材による豊富な情報量(文字の5000倍とも言われる)と、テストの自動採点や解説の即時確認が可能です。
オンライン授業が注目されている理由
コロナ禍での急激な普及
2020年3月から5月にかけて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として多くの学校で長期間の臨時休業が行われ、この期間にオンライン教育が実施されました。
このような疫病や地震などの災害時に、子どもたちが学習機会を失う事態に備え、「学びを止めない」ための対策としてオンライン授業の導入が急速に進みました。
実際、2020年5月時点の調査では、全国の高校教員の約7割が新型コロナウイルス感染拡大予防のためにオンライン授業を導入または導入予定と回答しています。
教育格差の解消と新しい教育様式
オンライン授業は、過疎化が進む地域や、不登校・病気療養などの事情で通学が困難な学習者に対し、教育機会の格差解消を担うツールとしての活用が期待されています。
また、講師や専門家が遠隔で授業を提供できるため、質の高い教育をより多くの学習者に提供できるという側面もあります。
今後は、教員による対面指導と遠隔・オンライン教育を組み合わせた新しい教育様式の実践(ハイブリッド化)が求められています。オンライン授業は、教育現場で活用される情報通信技術の総称である「ICT教育」の一環であり、「Education(教育)」と「Technology(テクノロジー)」を合わせた造語である「EdTech(エドテック)」にも含まれます。

オンライン授業の主な種類とそれぞれの特徴
オンライン授業は、主に「ライブ配信型」と「オンデマンド配信型」の2種類に大別され、これらを組み合わせた「ハイブリッド型」も存在します。
ライブ配信型(同時双方向型)
ライブ配信型は、リアルタイムで授業を配信する形式です。Web会議システム(ZoomやGoogle Meetなど)を活用し、教員と児童生徒が同時に接続し、映像や音声でやり取りを行います。
このタイプの最大の魅力は、遠隔地にいても教室にいるのと同様の臨場感で授業を受けられることです。
チャットやマイクを使ってリアルタイムで質問や意見交換が可能で、ディスカッションやグループワークも実施できます。授業時間が決まっているため、自宅学習のペースメーカー的な役割を果たし、学習のモチベーション維持につながります。
一方で、リアルタイムでのデータ送受信量が多いため、受講者・配信者双方の通信環境や端末性能に大きく左右され、途中で送受信が途絶える可能性があります。
また、教科書では伝わりにくい動作を伴う事柄や、実習・体験が必要な授業には不向きな場合があります。
オンデマンド配信型(録画型)
オンデマンド配信型は、あらかじめ収録された授業動画を、学習者が好きな時間に好きな場所で視聴する形式です。
この形式では、好きな時間に好きな場所で学習できるため、通学の手間や交通費が削減できます。
分からない部分を繰り返し視聴したり、自分のペースで学習を進めたりできるため、理解度を深めやすいのが特徴です。
ライブ配信型に比べてデータ通信量が比較的少なく済む傾向があり、動画教材の修正やアップデートが常時可能で、最新の動画を全学習者に一斉配信できます。
しかし、その場で質問したり、生徒同士が交流したりすることができないという課題があります。
強制力がないため、自主的に学習する意欲が求められ、飽きてしまう可能性もあります。教員側は生徒の学習状況をリアルタイムで把握しにくく、学習の進捗確認や学習者のモチベーション維持に工夫が必要です。
ハイブリッド型
ハイブリッド型は、対面授業とオンライン授業を組み合わせた形式です。「ハイフレックス型」では、教室で行われる対面授業を同時にオンラインでライブ配信し、生徒が通学困難な場合にオンラインで受講できます。
「ブレンド型」では、授業の目的に合わせて、対面授業、オンデマンド配信、ライブ配信を柔軟に組み合わせて学習を進めます。
ハイブリッド型のメリットとして、地域や事情を問わず授業が受けられること、感染症リスクの軽減、事前学習で理解度が高まり効率的な学習が可能になることが挙げられます。
ただし、対面とオンラインで資料や黒板の見え方が異なる場合があり、工夫が必要です。
オンライン授業を導入するメリット
学習者にとってのメリット
- 時間に縛られない
- 繰り返し視聴できる
- 質の高い教育を受けれる
- 登校できない児童に最適
オンライン授業は学習者にとって多くの利点をもたらします。
まず、時間や場所に縛られない柔軟な学習環境が実現できます。自宅や外出先など好きな場所で学習でき、通学時間や交通費の節約にもつながります。
オンデマンド形式では、分からない箇所を繰り返し視聴したり、自分のペースで学習を進めたりすることで、理解を深めることができます。これにより、個々の学習能力や理解度に応じた最適な学習が可能になります。
特に重要なのは、教育格差の解消と質の高い教育へのアクセスです。過疎地や離島に住む生徒でも、都市部の学校と同じ授業を受けたり、学内の教員では難しい専門分野の授業を外部の専門家や海外の講師から受けたりすることが容易になります。
また、自宅で受講できるため、通学途中の事故や事件に巻き込まれるリスクを軽減できます。
不登校や病気療養中の児童生徒が、体調の良い時にオンデマンド授業を視聴したり、ライブ配信で友人との交流機会を得たりすることも可能になります。
教育機関・提供側にとってのメリット
- 感染症対策ができる
- 運営費の削減
- 個別最適化
- 協働学習が可能
教育機関にとって、オンライン授業は運営面で大きなメリットをもたらします。感染症の流行や自然災害などにより学校に登校できない場合でも、授業を継続し、子どもたちの学びの機会を確保できます。
大規模な教室を用意する必要がないため、教室運営費の削減につながります。学校外の専門人材を招いた授業や、各校で学習動画を作成し配信することで、従来の授業ではできなかった教育を実現し、授業品質の均一化を図れます。
学習履歴の管理・個別最適化された学習の提供も重要なメリットです。オンライン授業は学習履歴が蓄積されやすく、これを活用することで、生徒一人ひとりの得意不得意を把握し、個々に最適化された授業や教材を提供することが可能になります。
協働学習ツールやチームコミュニケーションツールを活用することで、課題提示や回収、状況確認が効率的に行えます。
Web会議システムを活用したオンラインでの健康観察は、各家庭への連絡の手間を大幅に削減できます。
オンライン授業のデメリットと対策
- ネット環境や機材が必要
- 授業準備の負担が増加
- 生徒同士のコミュニケーションが困難
- 健康面への配慮
環境構築の課題
オンライン授業を行うためには、PCやカメラなどの機材、および安定したインターネット回線が不可欠です。特に初期費用や準備に手間取るリスクがあります。
この課題に対し、文部科学省が推進するGIGAスクール構想により、小中学校では「児童・生徒一人一台端末」と「高速大容量通信ネットワーク」の整備がほぼ完了しつつあり、高校でも令和6年度までに完了予定です。
地方自治体によっては、家庭にネット環境がない児童生徒のために、モバイルWi-Fiルーターの貸与や通信費補助を行っている場合もあります。
教材作成・授業準備の負担が増加
オンライン授業用の教材作成、特に動画教材の作成には、従来の授業準備とは異なる時間と労力がかかります。
この対策として、既存の授業資料を簡単にオンライン教材化できるツールや、ライブ配信した映像をオンデマンドで再配信できるサービスを活用することで、現場の負担を軽減できます。
理解度把握の課題
オンライン授業では、教員が児童生徒の表情や反応を直接見て理解度を把握することが難しく、集中力の維持が課題となることがあります。
Web会議システムのチャット機能やアンケート機能を活用して、生徒からの意見や理解度をこまめに確認することが重要です。
また、ディスカッションツールを活用したグループワークを積極的に取り入れることで、生徒間のコミュニケーションを促進し、双方向性を高めることができます。
LMS(学習管理システム)を導入し、学習履歴や進捗状況を管理することも有効です。
健康面への配慮が必要
長時間のオンライン授業は、目の疲れ、肩こり、難聴などにつながる可能性があります。
画面の前に座りっぱなしになるのではなく、30分おきに立ってストレッチを促す、90分以上の学習の際は画面から離れて休憩を入れるなど、提供側が学習者の健康状態にも配慮したガイドラインを設けることが望ましいです。
オンライン授業の導入に必要な準備とツール
事前準備と計画策定が重要
オンライン授業を成功させるためには、まず家庭のICT環境やネットワークの利用状況を確認し、不足している家庭への支援方法を検討しておくことが重要です。
また、どのような教育を実現したいかという「理想とする教育のイメージ」を明確にすることが必要です。
必要なICT機器とシステムを整理
学習者側では、パソコン、タブレット、またはスマートフォンなどのデバイスと、安定したインターネット回線が必要です。デバイスにカメラやマイクが内蔵されていることが望ましいです。

教員側では、PC、カメラ、マイクが基本となります。加えて、授業資料の提示には大型ディスプレイ、教材を映し出すためには実物投影機(書画カメラ)があると便利です。
WEB会議システムの導入
目的と用途に応じて、様々なシステムやツールを組み合わせることを推奨します。
Web会議システムでは、Zoomが大人数でのライブ配信授業が可能で、チャットでの質疑応答やアンケート機能、少人数でのディスカッションに使えるブレイクアウトルーム機能も備わっています。
Microsoft Teamsは会議、チャット、通話、共同作業ができるシステムで、大人数でのオンライン授業や、ファイル共有しながらの共同編集も可能です。
学習管理システム(LMS)は、学習者が教材を視聴したりテストを受けたりする「受講機能」と、教員や管理者が受講履歴や成績管理を行う「管理機能」があります。

オンライン授業の多様な活用事例
学校教育での活用
新型コロナウイルス感染症による長期臨時休業中、学校と家庭をつなぎ、児童生徒が学習機会を失わないための手段として活用されました。
京都府立鳥羽高校では、Webフォームで学習課題の質問を受け付け、回答を掲載する取り組みが行われました。
高森町立高森中学校では、ZOOMによる健康観察が実施され、伊那市立高森中学校ではschoolTaktを活用した協働学習が行われています。
愛知県日進市立日進中学校では、卒業証書授与式を全教室にライブ配信し、朝礼も校長室から生徒の顔が見える双方向性で実施しています。
参考:学びを止めない!これからの遠隔・オンライン教育~普段使いで質の高い学び・業務の効率化へ~
学習塾・予備校での展開
多くの学習塾や予備校で、録画型やLIVE型のオンライン授業が提供されています。
東進ハイスクールのように、オンライン授業を先駆的に導入し、高い合格実績を出している事例もあります。
株式会社シンドバッド・インターナショナルが運営する「大学受験専門・家庭教師メガスタディオンライン」では、離島の生徒が遠隔授業で難関大学に合格した例も報告されています。
企業研修とリカレント教育
グロービス経営大学院では、LIVE方式の映像授業で取得できる「オンラインMBA」を提供しています。
放送大学では、従来の放送授業に加え、オンデマンド講義やZoomを活用した同時双方向Web授業を充実させており、生涯学習やリカレント教育にも力を入れています。
株式会社学研プラスでは、外国人従業員向けの日本語学習サービスにeラーニングを導入し、個々人のペースに合わせた言語力向上を実現しています。
オンライン習い事の拡大
コロナ禍の影響で、オンラインジムやヨガ、サークル活動など、自宅で手軽にレッスンを受けられるオンライン習い事も広がっています。
SOELUでは、インストラクターと複数の受講生を結ぶライブレッスンを提供し、受講生のプライバシーを守りながら自宅でのレッスンを可能にしています。
オンライン授業のポイント
明確な目標設定と事例研究
オンライン授業で「どのような教育を実現したいか」という具体的なゴールイメージを描くことが大切です。
多くの成功事例や失敗事例の情報を収集し、参考にすることで、自校・自組織にとっての最適な活用方法を見出す手助けとなります。
段階的な導入とノウハウ蓄積
LMSの教材登録や学習者登録、受講といった一連の流れを事前に体験するなど、小さく始めてトライ&エラーを繰り返すことで、本格的なプロジェクト始動前に課題を洗い出し、経験とノウハウを積むことが理想的です。
組織内協力体制の構築
校内や組織内で「もっとこういう授業を実施したい」という教育への熱意を持つ理解者や応援者を増やし、協力を得ながらプロジェクトを進めることが非常に重要です。
日常的なICT活用の推進
緊急時になってからICTツールの使い方を学ぶのは困難です。
日常の授業から積極的にICTツールを活用し、教員も児童生徒も使い方に慣れておくことが望ましいです。
また、タイピングや情報モラルなど、基本的な情報活用能力の育成も平時から進めておく必要があります。

継続的な支援とフォローアップ
オンデマンド型では受講者の自律性が求められるため、配信側は受講状況を定期的に確認し、適切な受講促進を行う必要があります。ライブ配信型授業で受講者が急遽不参加になったり、途中で受講中断してしまったりするケースに備え、ライブ配信内容を録画収録しておくことで、後々のリカバリがしやすくなります。
まとめ
オンライン授業は、インターネットを介して時間や場所に縛られずに学習機会を提供する、現代の教育において不可欠な手段です。
新型コロナウイルス感染症の流行を契機に急速に普及し、災害時でも学びを止めないための対策として、また教育格差の解消や質の高い教育へのアクセス向上に貢献しています。
ライブ配信型、オンデマンド配信型、そして両者を組み合わせたハイブリッド型といった多様な形式により、柔軟な学習環境の提供、効率的な運営、個別最適化された学びの実現が可能になっています。
一方で、技術的な課題や教材作成の負担、コミュニケーションの難しさなどのデメリットも存在しますが、適切な対策と支援体制により克服することができます。
学校教育から企業研修、リカレント教育まで幅広い分野で活用が進んでおり、将来的には対面指導と遠隔・オンライン教育を組み合わせた新しい教育様式が定着していくことが期待されます。
成功の鍵は、明確な目標設定、段階的な導入、組織内協力、そして継続的な支援にあります。
オンライン授業は、教育市場を大きく広げ、学習者一人ひとりに寄り添う学びを実現する可能性を秘めている重要な教育手段と言えるでしょう。




